令和7年度 岐阜県在宅医療推進センター運営事業 在宅医療ACP普及啓発事業「岐阜県医師会版エンディングノート『これからノート』活用研修会」(2025/8/31開催)
医師研修会テーマ:“これからノート”でつなぐ意思決定支援と多職種連携の実践
岐阜県在宅医療推進センター運営事業の一環として、岐阜県医師会版エンディングノート「これからノート」の活用法と多職種での意思決定支援の実践をテーマに、2025年8月31日(日)に岐阜県医師会館にて研修会を開催しました。第1部では「“これからノート”の症例別活用法について」、第2部では「“これからノート”を使った意思決定支援と連携実践」と題してグループ研修を行いました。

岐阜県医師会館1階大会議室
開会の挨拶
はじめに、岐阜県医師会の伊在井みどり会長より「“これからノート”を在宅医療や看取り現場で活用してほしい」「高齢者救急の課題解決に“これからノート”を役立てたい」「高齢者の6疾患が増加傾向にあり、訪問看護ステーションの役割が大きくなっている」「研修会を通して多職種連携を深めてほしい」などの挨拶で開会しました。

開会の挨拶 伊在井みどり会長
第1部「“これからノート”の症例別活用法について」
第1部では、岐阜県医師会の佐竹真一常務理事が登壇し、「“これからノート”の症例別活用法について」と題して、岐阜県医師会が中心となって作成した「これからノート(エンディングノート)」の特徴や、活用方法と効果、想定される活用シーンなどについて説明しました。

第1部講演の様子

佐竹真一常務理事
「これからノート」とは
「これからノート」は、岐阜県医師会が中心となって、令和5年度から6年度にかけてワーキンググループで検討・作成した、病気を中心とした在宅医療・ACP(人生の最終段階における医療やケアについての話し合い)支援ツールです。地域におけるエンディングノートの普及不足、在宅医療・看取り現場で意思決定支援ツールが求められている現状、そして救急現場での患者の意思尊重の課題解決を目指し作り上げました。
大きな特徴は、病気ごとの治療・ケアの希望を詳細に記載できる点です。患者自身が記入しやすく、患者の希望やこれまでの経緯を本人や家族だけでなく多職種で共有できるよう構成し、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に準拠して作成しました。
特に「わたしの病への想い」のページでは、自分の病気を正しく理解し、病気に対する想いや不安を記入できる点も特徴的です。今後の治療・ケアの希望を家族や医療スタッフに共有し、想いの変化も記入できるようになっています。また、巻末には「心肺蘇生に関する医師の指示書」を掲載し、本人の意思に反して救急車を呼んでしまった場合にどのような問題があるのかをわかりやすく解説しています。
活用方法と期待される効果
「これからノート」を活用することで、患者本人と家族、多職種間において「情報収集」「話し合い」「記録・共有」「見直し」という4ステップを円滑に行うことができます。患者が自身の希望や価値観を記入することで「情報収集」を行い、その情報に基づいて家族や医療者と将来の医療・ケアについて「話し合い」、意思決定した内容を多職種で「記録・共有」し、患者自身の状態や希望の変化に応じて、内容を常に「見直し」ていくことができます。
講演では、3つの模擬症例を用いて具体的な活用シーンを紹介しました。
■模擬症例1:「80歳男性、在宅療養中の慢性心不全」
・訪問看護師が急な呼吸苦に対応する場面で、あらかじめ「本人は入院を望まない」と記録されており、家族も共有していることで、救急搬送の是非を迷わず判断できる。
・ケアマネジャーがサービスを調整する場面で、病状の変化や家族の介護負担への不安が具体的に記録されているため、介護サービス(訪問介護・短期入所など)の導入が根拠を持って検討できる。
・急変時に医師が指示を出す場面で、「急変時も在宅での対応を希望」と記載があったため、医師も安心して緩和ケアの方針を継続できる。
■模擬症例2:「65歳男性、がん終末期、緩和ケア中」
・緩和ケアチームの情報共有の場面で、本人の「苦痛を最小限にしてほしい」という希望が明示されており、医療者全体が同じ目標を共有して対応できる。
・看護師や医師が、夜間対応する場面で、「延命治療は望まない」という方針が共有されているため、家族にも「このまま看ていきましょう」と安心して説明できる。
・本人の意識が低下して意思確認できない場合に、「最期は自宅で家族と」という記録があり、家族・医療者のよりどころとなる。
■模擬症例3:「70歳女性、在宅療養中の中等度認知症」
・ケアマネジャーがサービス担当者会議を開く時に、本人の「自宅が落ち着く」という言葉や、家族の介護負担への不安が共有されているため、本人の意思を尊重した在宅継続の支援計画が立てやすい。
・デイサービス職員が、本人の状態を理解する際、症状の変化や不安感が具体的に記載されており、対応方法(声かけ、環境調整など)に活かされる。
・将来的な施設入所の検討時に、「できる限り在宅希望」と本人・家族の意向が確認できるため、慎重な話し合いが可能になる。
こうした模擬症例をもとに考えると「自宅療養や施設利用、介護サービス導入時」「体調悪化時・入院時・意思疎通困難時」「延命処置や死亡場所、看取りに関する希望」など幅広い活用シーンが想定されます。また、医師や訪問看護師、ケアマネジャー、地域包括支援センターなど、どの立場の方からお渡ししても差し支えありません。
まとめ
「これからノート」は、病気を中心とした、おそらく初のエンディングノートです。
「病気に対してしっかり理解し、今後の病状の見込みがわかった上で、延命処置の選択をしてもらえる」「終末期の状態、救急搬送の説明をすることで、家族が迷わず安心して自宅で看取る体制ができる」などの効果が考えられます。
在宅医療の導入の手引書として、多職種での情報共有をスムーズにするツールとして、「これからノート」をご活用ください。とまとめて、講演を閉じました。
第2部「“これからノート”を使った意思決定支援と連携実践」
県北西部地域医療センターセンター長兼国保白鳥病院院長補佐、自治医科大学地域医療学センター地域医療支援部門教授 後藤忠雄先生
第2部では、これまで数回に渡って開催したACPのロールプレイ研修などで評判の後藤先生を講師にお招きし、「“これからノート”を使った意思決定支援と連携実践」と題して、グループワーク研修を実施しました。

県北西部地域医療センターセンター長兼国保白鳥病院院長補佐、自治医科大学地域医療学センター地域医療支援部門教授 後藤忠雄先生
研修の目的
このグループワークでは、参加者が「これからノート」を導入する場面を具体的にイメージし、コミュニケーションの重要性を認識した上で、その活用方法を他者に説明できるようになることを目的として実施しました。
グループワーク1:どんな場面でノートを渡すか?
6人ずつグループに分かれて、アイスブレイクを兼ねた自己紹介からスタート。「どんな場面でノートを渡すことができそうか」をテーマに、ロールプレイを行いました。参加者は「どんな対象者に」「どんな場面で」渡すかシーンを思い浮かべて白紙に記入して、グループ内で共有。3人1組になって「ノートを渡す役」「ノートを渡される役」「会話の観察者」になって、「これからノート」を渡すシーンを自由に演じました。
「優しい声で伝えるとよい」「全部書かなくてもよいと伝えると安心する」「こういうものがあると知るだけでもいい」など、渡す人、渡される人、観察する人、それぞれの感想を通して、どのような声かけで、どのように渡すとよいのかを話し合う場となりました。

第2部講演の様子
グループワーク2:患者宅でのカンファレンスを再現
研修当日に即席で結成された劇団「けんぎふいの会」が模擬症例をステージで披露。後藤先生の名演技に笑いが巻き起こるなか、「これからノート」を使うコツや特徴が紹介されました。
1人ずつ用意されたシナリオを読み込み、その人の気持ちになって「これからノート」を記入。その後、本人役が書いたノートをもとに、本人、家族、かかりつけ医、訪問看護師、ケアマネジャー、それぞれの役になりきって、シナリオに沿って患者宅でのカンファレンスをロールプレイ形式で再現しました。

即席の劇団「けんぎふいの会」
「これからノート」のよいところは個人の想いを書き込むだけでなく、家族を含めた支援者とのコミュニケーションも書き込めるところです。ケアマネジャー役が司会となってカンファレンスで引き出したご本人や家族の気持ちをノートに追記していく場面も再現されました。
アドリブも交えた活気あるロールプレイの後には、グループ同士で拍手が起こる場面も見られました。
「本人の気持ちがすでに書いてあることで、直接的でなく、あいまいに質問ができる」「ノートに沿って記録することで振り返りがしやすい」「コミュニケーションのツールとして役立つ」といった感想が共有され、「本人がどうしてほしいのか本人の想いを丁寧に拾い集めること」の重要性が再認識されました。
本人の想いを拾い集めるためにはコミュニケーションが大切であると、想いを拾い集めるコツや「非言語的」「準言語的」「言語的」などのコミュニケーションスキルについて後藤先生から解説がありました。
グループワーク3:「これからノート」の活用
残りの時間では「“これからノート”を活用するために」というテーマでグループで話し合いました。模造紙に各自が思いついたことを書き込み、多岐にわたるコメントで埋め尽くされました。
「“これからノート”の存在をいろんな人に広めたい」「よりよく生きるために活用したい」「人生の最期に後悔しないよう考えるためのツールにしたい」「口では伝えにくいことも書くことで伝えられる」「在宅療養者との交換日記にしたい」「書けるところから書いてもらう、まずは自分から」「妻へのラブレター、子どもへの贈り物になる」といった心温まるコメントまで、様々な視点からノートの可能性が語られました。
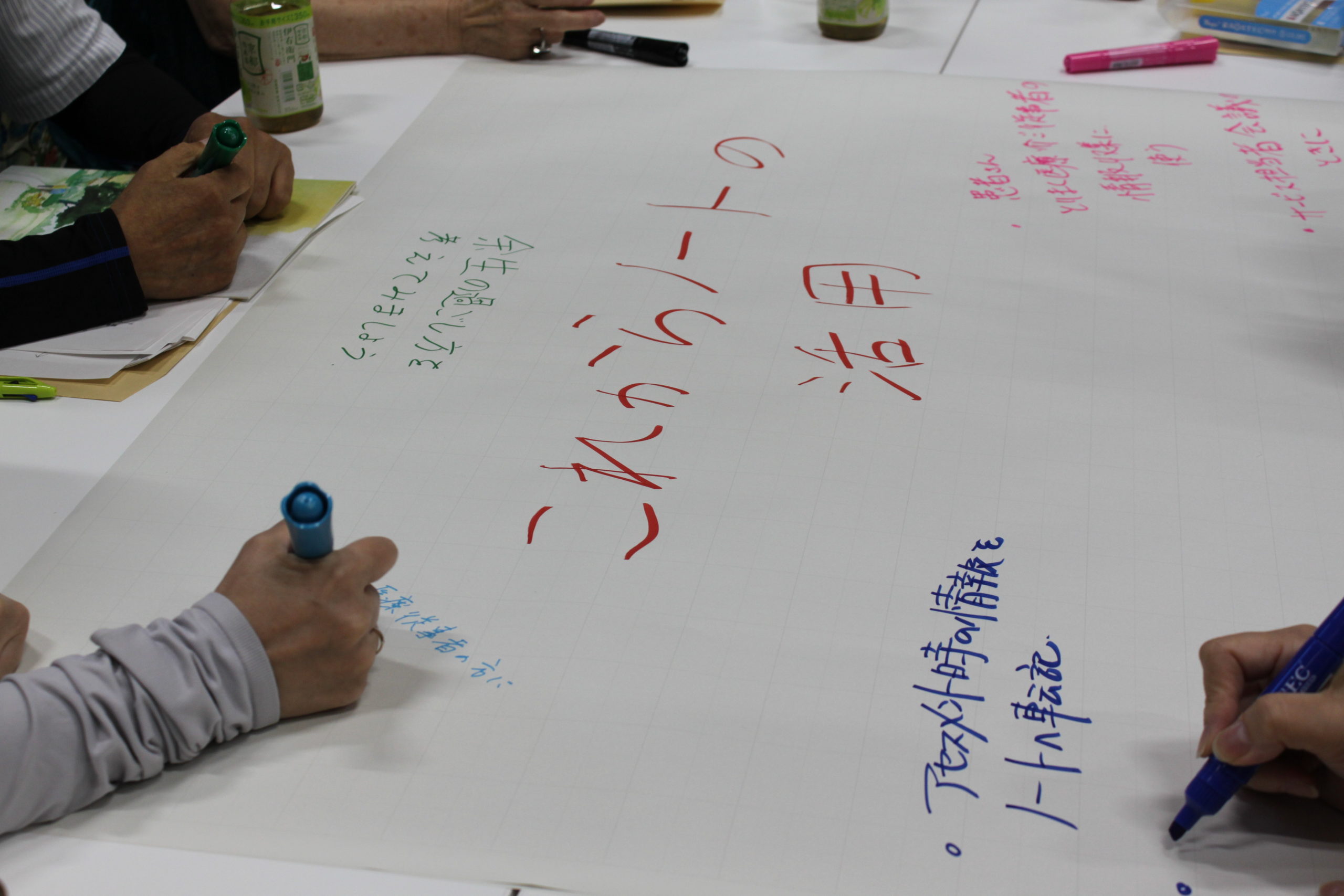
模造紙に感想を書き込む参加者
最後に、「“これからノート”を使った意思決定支援では、意思表示ができるうちに本人の想いを拾い集めておかなければなりません。“これからノート”は、本人・家族・専門家との双方向のノート。 “これから”のノートであり「どう生き、どう逝くか」を話し合うためのツールです。このノートを渡す時、使う時にどんな配慮や言葉がけができるかが大切。いろんな機会を見つけて、本人、家族とよい関係性を築いた上で“これからノート”を活用してください」と後藤先生の言葉でグループ研修が締めくくられました。

握手をして本日の研修会を讃え合うグループ
